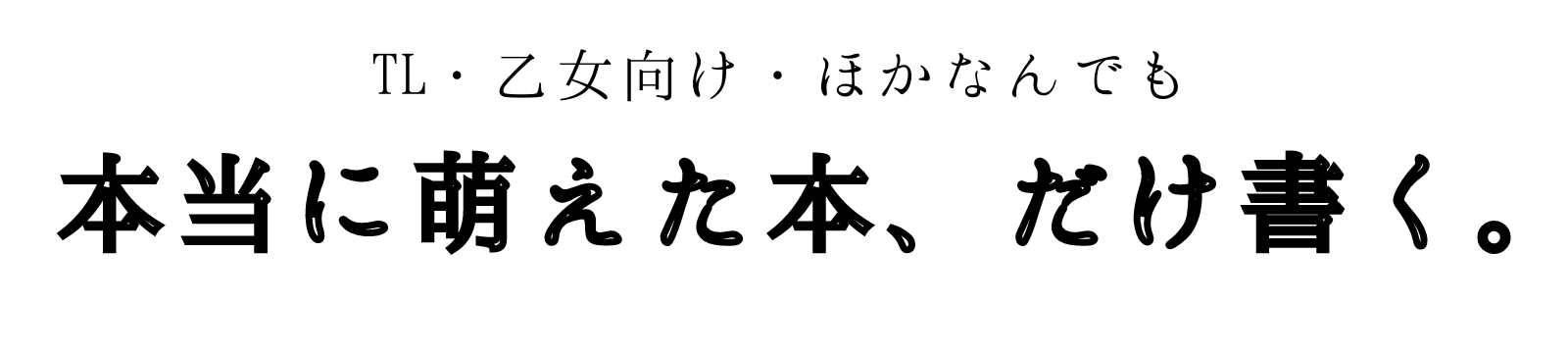映画「ウォルト・ディズニーの約束」を観ました。名作ミュージカル映画「メリー・ポピンズ」の誕生秘話を描いた作品です。
観たきっかけは、椎名高志さんのポストでした。
2月9日のポストで椎名高志さんが「いろいろしんどい」と言っているのは、2024年1月29日に亡くなった芦原妃名子さんのことが関係していると思われます。2月6日には、小学館が「今回の件に関する経緯を社外に発信する予定はない」という趣旨の社員向け説明会を行ったという内容がスクープされました。8日には現場の編集者が「作家の皆様 読者の皆様 関係者の皆様へ」というタイトルで声明を発表しています。痛ましい出来事の経緯や、小学館、日テレ、そのほか関係者の姿勢などがネットを中心にかなり議論を呼んでいました。
椎名高志さんのポストをきっかけに「ウォルト・ディズニーの約束」という作品を知り、
- 人気作品を原作とした映画製作の裏側を描いている
- 原作者のP.L.トラヴァースが映像化に乗り気ではなく、脚本にもいろいろ意見を言っている
ということで興味を惹かれました。原作者が追い詰められる構造の理解に役立つかもしれないと思ったからです。
ただ私、お恥ずかしながら「メアリー・ポピンズ」の児童文学もミュージカル映画も通ってないんですよね……。
ということで、「風にのってきたメアリー・ポピンズ」(原作の児童文学)を読破し、ミュージカル映画「メリー・ポピンズ」を鑑賞しました。
そのうえで「ウォルト・ディズニーの約束」を観た感想です。

このブログでは児童文学は「メアリー・ポピンズ」、ディズニーのミュージカル映画は「メリー・ポピンズ」と表記しています。
「風にのってきたメアリー・ポピンズ」と「メリー・ポピンズ」の違い
まず、児童文学の「風にのってきたメアリー・ポピンズ」とミュージカル映画の「メリー・ポピンズ」、2作の違いについて書きます。違うから悪いと言うつもりはありません。
2作はけっこう別物でした。
児童文学の「メアリー・ポピンズ」は、メアリー・ポピンズというナニー(子供の保育・教育をする人)が物語の中心。バンクス家の子供たちは、彼女の不思議な力と何をも恐れぬ堂々とした態度を畏怖しながらも、魅せられていきます。
一方、ミュージカル映画の「メリー・ポピンズ」ではバンクス一家、特に父親に焦点が当たっています。厳格で仕事一筋、なんでも自分の思い通りになると思っている父親が、子供たちの大切さに気づく……つまり家族が再生する物語でした。メリー・ポピンズの役割は、子供たちを楽しませる、ちょっと不思議なナニーといったところです。
結論から書くと、原作の児童文学からミュージカル映画になって変わった点は、大きく2つあると思っています。
- 神秘性が薄れたメアリー・ポピンズの描かれ方
- バンクス家の父親に焦点が当たり、テーマが「家族の物語」に
児童文学のメアリー・ポピンズには、神秘的なところがあります。
私は「風にのってきたメアリー・ポピンズ」のなかでも「踊る牝牛」のエピソードが気に入ったのですが、そこにはメアリー・ポピンズの母親の描写が少し出てくるんです。高い月さえ飛び越えられる、神話に出てくるような赤牛が最後に助言を求めたのがメアリー・ポピンズの母。そして「満月」のエピソードでは、動物の世界の王様であるキング・コブラがメアリー・ポピンズに「いとこよ」と呼びかけます。母方のいとこの子だそうです。
素性がはっきりとは書かれていませんが、メアリー・ポピンズに対して“超常的な存在”の子供というイメージを抱きました。まだ人や動物や星が分離していないときから存在する“何か”の子供。メアリー・ポピンズは魔法のような不思議な力を使うけど、魔女というよりは妖精っぽい。神話やおとぎ話の登場人物のような神秘性を感じるキャラクターなのです。
もちろんそれだけではなくて、自分の姿をショーウィンドウで見るのが大好きなかわいいところや、バンクス家の子供たちを不機嫌さでコントロールしようとする辛辣さを持っています。けっこう人間味があります。
東風に乗ってやってきたメアリー・ポピンズは、西風が吹くとともにバンクス家から去っていきます。子供たちは彼女と離れるのが嫌で泣き叫ぶのですが、最終的にはメアリー・ポピンズの「オー・ルヴォワール(また会うまで)」という言葉を胸に別れを受け入れます。
マイケルは、ほっとしたように、ながいため息をついて、「まあ、いいや。」とふるえ声でいいました。「メアリー・ポピンズは、いつも、するっていったようにするんだから。」
「風にのってきたメアリー・ポピンズ」(岩波少年文庫)
マイケル、子供なのになんという諦念! メアリー・ポピンズに振り回されるのに慣れてる(笑)。
バンクス家の子供たちにとって、メアリー・ポピンズは恐竜とか象とか、自分ではどうにもならないものの象徴なのかもしれません。大きくて魅力的で、でも気難しくて対応を間違えると悲劇が起こるけどどうしても惹かれてしまうのです。
ミュージカル映画のメリー・ポピンズには、そういった神秘性はあまり感じません。魔法を使って不思議な体験をさせてくれる、“可愛くて優しい、不思議なナニー”といった印象です。
このメアリー・ポピンズの描かれ方の違いはどこから来るのか?と考えると、「テーマの違い」、そして「ディズニーのミュージカル映画であること」が大きいのかもなーと思いました。
前述した通り、ミュージカル映画の「メリー・ポピンズ」はバンクス家の父親にスポットを当てています。「風にのってきたメアリー・ポピンズ」ではほぼ序盤くらいしか登場しなかった父親ですが、映画では最初から最後までかなりの存在感。というか、仕事人間だった父親が本当に大切なものは仕事ではなく子供や妻であることに気づく、というのが映画のストーリーラインで、劇中で精神的に一番変化したのは間違いなく父親です。
映画は、バンクス家の両親と子供たちが一緒に笑顔で凧揚げをするシーンで終わります。子供たちが壊してしまった凧を、父親が終盤に自らの手で修理するのはわかりやすいメタファーでしょう。
映画は「家族の再生の物語」として描かれているんですね。
原作でメアリー・ポピンズとの別れにあれだけ泣き叫んだ子供たちは両親との凧揚げに夢中。メリー・ポピンズは1人で旅立ち、バートだけが空に舞い上がる彼女を見送ります。
これは憶測ですが、神秘的な存在であるメアリー・ポピンズに子供たちが夢中になってしまったら、両親の存在感が薄れてしまうから映画ではこういった脚本になったのかもしれません。
また、そもそもですが原作の気難しく厳格なメアリー・ポピンズだったら、煙突掃除夫たちと屋根の上で歌ったり踊ったりしなそう(笑)。バートにだけは優しく思いやりを示すメアリー・ポピンズですが、身知らずの煙突掃除夫には冷たい視線を送ることでしょう。「ディズニーのミュージカル映画であること」とメアリー・ポピンズの神秘性は相性が悪いのかもしれません。
ほかにも
- 原作の「外出日」というメアリー・ポピンズと親友バートの2人だけの交流エピソードが、映画では子供たちを交えてアニメと実写の融合シーンになった
- 映画ではバンクス家の母親が女性参政権運動に熱中
など、細かい違いはけっこうあります。
個人的に好きなのは「風にのってきたメアリー・ポピンズ」ですが、映画の「メリー・ポピンズ」も面白かったです。実写のメリー・ポピンズたちとアニメの動物たちが一緒に踊ったり、競馬をしたりするシーンは「1964年にこんなことができたんだ!」といまさら新鮮に驚きました。
また言うまでもないことですが、名曲揃い。「チム・チム・チェリー」「お砂糖ひとさじで」「スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス」「2ペンスを鳩に」など、Apple Musicで速攻ダウンロードしました。
「ウォルト・ディズニーの約束」は映画としては名作
原作小説とミュージカル映画の溝を埋める作品
そして「ウォルト・ディズニーの約束」の感想です。
前提として、「ウォルト・ディズニーの約束」も「メリー・ポピンズ」もどちらもディズニー映画です。そして「ウォルト・ディズニーの約束」は史実ではなく、史実にインスピレーションを受けたフィクション映画。なのでディズニー側にとって本当に都合の悪いことを描くことはほぼないでしょう。
という前提のうえで観た感想を簡単に書くと、「原作とミュージカル映画、けっこう違うなー」と思っていたその溝を埋めてくれる作品でした。
あらすじを引用します。
長年にわたり『メリー・ポピンズ』映画化を目指すウォルト・ディズニー(トム・ハンクス)は、ついに原作者P.L.トラヴァース(エマ・トンプソン)と共に映画の製作に入る。
しかし、彼女は提案する脚本やアイデアをことごとく否定しはじめ、製作は難航していく。なぜ彼女は頑なに映画化を阻むのか。名作映画誕生に隠された真実とは。
https://www.disney.co.jp/studio/liveaction/1253
「ウォルト・ディズニーの約束」開始3分、「彼女でお金儲けなんて私は地獄行きよ」というトラヴァースの言葉でいきなり泣きそうになります。
トラヴァースの言う「彼女」とは、もちろんメアリー・ポピンズ。
「風にのってきたメアリー・ポピンズ」の訳者あとがきに、トラヴァースの言葉が紹介されています。
「わたしとしては、いっときたりとも、わたしがメアリー・ポピンズを作りだしたなどと思ったことはありません。きっと、メアリー・ポピンズが、わたしを作りだしたのだと思います……」
「風にのってきたメアリー・ポピンズ」訳者あとがき(岩波少年文庫)
トラヴァースにとってメアリー・ポピンズは自分で生み出した物語のキャラクターではなく、かけがえのない存在でした。そんな大切なメアリー・ポピンズは、ディズニー映画の登場キャラクターになったらきっと陽気になり、ハッピーエンドに組み込まれてしまう。
ではなぜ映画化を承諾したのか。「ウォルト・ディズニーの約束」では、トラヴァースの経済状況が理由として描かれていました。本の売れ行きが悪くなり、家を手放す寸前。なのでディズニーからの「メアリー・ポピンズ」実写化は、経済的に一すじの光明だったのです。
ちなみに、映画化の話はいきなり降って湧いたわけではありません。「メリー・ポピンズ」の映画が公開されたのは1964年。それより20年以上前、1938年に「風にのってきたメアリー・ポピンズ」を愛読していたウォルトの娘が同作の映画化を望み、ウォルトはそれを叶えるために動き出します。1度目の交渉はあっさり断られ、1940年代の交渉でもトラヴァースの返事はノー。1959年の申し込みでついに映画化を認めます(資料によっては1961年とあり、ちょっと曖昧です)。
つまりディズニーにとっては20年来の映画化プロジェクト。
「ウォルト・ディズニーの約束」冒頭は、ようやくトラヴァースが「映画化の話し合いに応じる」という段階です。トラヴァースはイギリスからディズニースタジオのあるロサンゼルスに行き、映画のアイデアを聞こうとします。
ディズニー側にとっても気合いの入ったプロジェクトなので、魅力的な絵コンテ、作詞・作曲を手がけるシャーマン兄弟の生演奏、数々のおもてなしで、彼女の心を掴もうとします。
でもトラヴァースはディズニー側の提案をほとんどすべて否定!
彼女は映画の中で、かなり気難しく、頑固で、他人の好意を跳ね除ける人間として描かれています。
脚本、美術、音楽、何も譲らない。
中でも「脚本を読む会」のエピソードはすごいです。「メリー・ポピンズ」の脚本をいちから朗読させ、少しでも納得できなかったらすかさず「NO!」と言って直すまで議論。ディズニー側の粘り強い交渉も、トラヴァースの妥協しない姿勢も、クリエイターとして最善を尽くしているあらわれです。この両者の議論こそが映画のキモ。
でもウォルトも、脚本家も、シャーマン兄弟も、そしてトラヴァースもイライラして疲弊していって、私も観ていて「この映画化、誰も幸せにしないな……」とつらくなっていく。
それでも少しずつ交流を重ね、一歩進んで二歩下がりを繰り返し、映画化プロジェクトは進んでいきます。
そして、トラヴァースの過去も紐解かれていきます。彼女には大好きな父親を失った消えない傷があり、その記憶が今でも彼女を苦しめているのです。父親との関係に苦しんだという意味では、ウォルト・ディズニーも同様でした。
詳細はぜひ映画を観てほしいのですが、ここで「『メリー・ポピンズ』がなぜ(原作ではほぼ出番がなかった)父親に焦点を当てているのか」に納得感が出るんですね。
映画も邦題は「ウォルト・ディズニーの約束」ですが、英語だと「SAVING MR.BANKS」。
つまり「バンクス氏(バンクス家の父親)を救う」なんです。
映画としても面白くて、「原作とミュージカル映画、けっこう違うなー」と思っていたのを補完してくれて、観てよかった作品です。
余談ですが、トラヴァースのファッションがめちゃくちゃ素敵。私も初老になったらトラヴァース(というかエマ・トンプソン)みたいに上品に決めたい!と思いました。
原作者と原作の扱いでモヤる
というのが「ウォルト・ディズニーの約束」の感想なんですが、映画の完成度とは別の尺度でモヤっとするところが多くて。
なぜトラヴァースがあそこまで頑なだったかというと、メアリー・ポピンズへの誠実さと罪悪感ゆえ。
ですが、結局トラヴァースが頑なに拒否したアニメーションは「メリー・ポピンズ」で採用され、メアリー・ポピンズは気の強さはあるものの優しくかわいい人柄になり、ミュージカルで陽気に歌い、トラヴァースが「???」となっていた「スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス」という謎の言葉も物語のキーになっています。結果的にはウォルトの意向に沿ったものになっていた。
現代の日本だったら原作者が持つ「著作者人格権」の「同一性保持権」が侵害されてる事例です。これは「自分の著作物の内容又は題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利」という権利で、平たく言うと「原作者が納得しない改変はNG(納得してたら改変OK)」ってやつですね。ただ「ウォルト・ディズニーの約束」はフィクションだし、描かれていない部分もたくさんあるだろうし、何より1960年代のアメリカの法律に関してはまったくわかりません。
また、「脚本を読む会」をはじめ、ロス滞在中のトラヴァースの孤独は観ていてつらいものがありました。「脚本を読む会」ではウォルト、脚本家、シャーマン兄弟というディズニー側と、トラヴァースの対立構図。たったひとりで自分の作品である「メアリー・ポピンズ」を守らなくてはならないのです。ニューヨークに疎開経験があるとはいえロサンゼルスというアウェーで、編集者やエージェントもおらず、寝るときも食べるときもずっとひとりで気難しい顔をして。孤独に自分の過去、そして作品と向き合っていました。唯一心を開けた運転手との交流が一服の清涼剤でしたね。
「ウォルト・ディズニーの約束」は事実にインスピレーションを受けたフィクションですが、作品とキャラクターへの責任感、原作者の意見が通らないむなしさと憤り、わかり合えない孤独、アウェーでひとり戦うつらさというトラヴァースの感情は真に迫るものがあります。
「私だったら絶対に途中で折れて手を引き、すべてを任せちゃうな……」と感じました。
映画の最後、トラヴァースの肉声が流れます。「脚本を読む会」でエビデンスのために彼女が指示して回していたテープが残っていて、それが聞けるんです。それが本当に跳ね除けるような「NO!」で(脚本家にとってもマジでつらい記憶だろうな……)。
もちろん、実際のトラヴァースが「脚本を読む会」をどう思っていたかはわかりません。
トラヴァースたちは、クリエイター同士の直接の話し合いという形式を取りました。間に入っている人がいないという点で、誤解の少ないやりとりができたとも言えます。ひるがえすと、意見の対立もやむなしなところはあります。
でも、理想を言うなら目標を全員で共有して、誰かが孤立しない構図(第三者的な立ち位置の調停者を入れるとか)で、心理的な安全性を確保する場を形成するのが大事かなあと。
本作を観るきっかけがそもそも……というところもありますが、今の私はどうしても芦原さんのことを考えながら観てしまいます。今はこういう見方をしていますが、もし2024年より過去に見ていたとしたら原作者の意向が蔑ろにされている(ように見える)ことと、原作者の孤独という問題を私が気にしたか?「いい映画」としてだけ消費したのではないか?というところも考えましたが、結局答えはわかりません。
ただ、映像化プロジェクト、そしてクリエイター同士のやり取りの解像度が上がる作品です。興味がある人はぜひ観てみてください。
おすすめの見る順番は、
1.「風にのってきたメアリー・ポピンズ」
2.「メリー・ポピンズ」
3.「ウォルト・ディズニーの約束」
です。この順番で見ないと、「ウォルト・ディズニーの約束」のトラヴァースの悩みがわかりづらいかもしれません。
まだ映像の関連作も多くて、私はこれから「ディズニー映画の名曲を作った兄弟:シャーマン・ブラザーズ」と「メリー・ポピンズ リターンズ」を観ようと思っています。